環境土木工学科
岡崎 泰幸
教員紹介
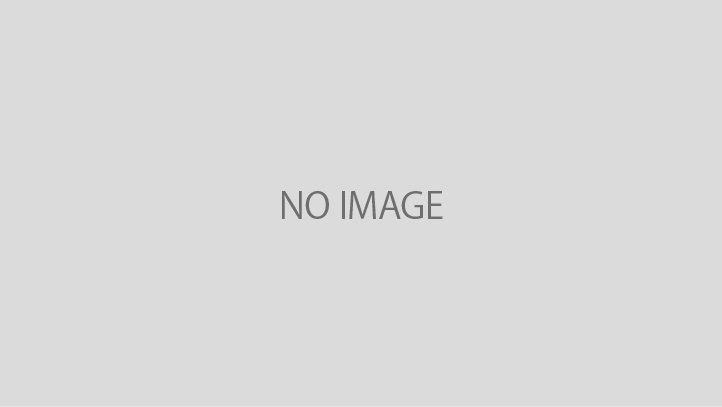
岡崎 泰幸OKAZAKI Yasuyuki
工学部 環境土木工学科 講師
プロフィール
- 【専門分野】
-
○トンネル工学
○岩盤工学
- 【担当科目】
- 土木基礎工学 、 地盤工学Ⅰ/Ⅱ 、 都市総合工学A 、 地盤基礎工学 、 建設工学実験 など
- 【研究テーマ】
-
1.トンネル・坑道の設計の高度化に関する研究
2.トンネル施工時の安全性の向上等に関する研究
3.トンネル・地下遺跡の維持管理に関する研究
- 【ひとこと】
「現状維持は後退」という言葉があります。1年前の自分より少しでも成長できるように、自ら目標を設定して日々取り組んでいってください。貴重な学生生活をぜひ有意義なものに。
