電子情報工学科
江田 英雄
教員紹介
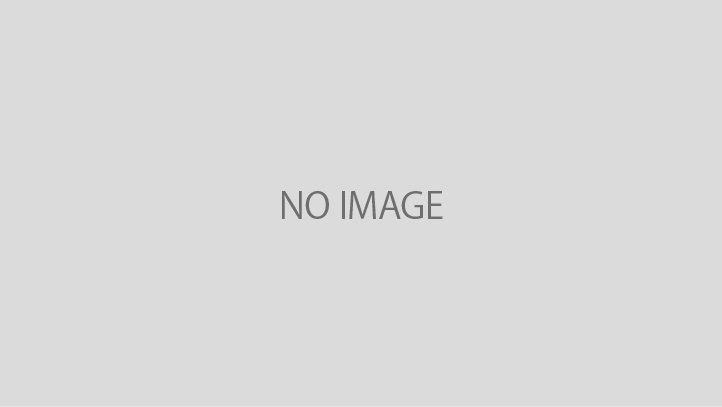
江田 英雄Eda Hideo
工学部 電子情報工学科 教授
プロフィール
- 【専門分野】
-
○Medical Optics
○脳研究
○計測分野(光や電磁気を用いて、主に生体を対象として)
○知的財産戦略と標準化戦略
○事業化戦略
- 【担当科目】
- 画像とマルチメディア 、 アーキテクチャとOS 、 数理統計学B 、 プログラミングB 、 電気化学
- 【研究テーマ】
-
1.近赤外光を用いた脳活動計測
2.濁った系での光散乱理論、その逆問題解析
3.意識、視覚情報
4.音楽と脳活動
5.カフレス血圧計測
6.国際標準化
7.電気電子回路とソフトウエア視点からの新製品開発
8.新商品開発、規制対応
9.デザイン、QFD
10.ビジネスプロデュース
- 【ひとこと】
技術は社会に普及してはじめて意味を持ちます。そのために2点。新しい知見にもとづく技術を創り出すこと、その技術を利用した製品を商品レベルまでもっていって世に出すこと、が大切です。第一の点には、光を使った計測技術、脳研究などの分野で基礎研究から応用研究まで新しい研究を進めます。第二の点には、知的財産戦略、国際標準化戦略、ビジネス戦略を進めます。工学者がただの思い込みで活動するのではなく、きちんと社会との接点を持つ。自分の足元を見つつ、顧客の声、世間の情勢などをふまえて、それらを基礎研究にも活かしましょう。国際規格ISOとIECで国際コンビナに就任した経験、大学発ベンチャーを起業した経験をふまえて、有意義な学生生活となるようサポートします。工業大学出身者として最低限必要な知識、スキル、コンピテンシーを鍛えましょう。
